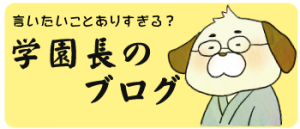![]()
前回のブログで世界中には約200の国・地域があることを紹介しました。
これらの国の大部分は、建国記念日を法律で定めて祝日としています。
日本国では、日本神話を基に、「建国をしのび、国を愛する心を養う日」として、1966(昭和41)年に2月11日を建国記念の日と定めました。
私たちが普段使用する「西暦」とは、キリスト教でキリスト(救世主)と見なされるイエス・キリストが生まれたとされる年の翌年を元年(紀元)としたものです。
一方、日本独自の皇紀は、古事記や日本書紀で初代天皇とされる神武天皇の即位日を皇紀元年1月1日とし、そこから日本の歴史が始まったとする考え方で、現在の暦(新暦)では2月11日になります。
ですから、日本国の歴史は西洋の歴史よりも660年も古く伝統があるのです。
初代天皇である神武天皇が即位したとされる年を元年とする日本の紀年法を皇紀としますが、明治以前は「元号」や「干支」を使用(あるいはそれらを併用)しており、ある年を基準として経過年と遡及年により年を数える「紀元」という方法を用いませんでした。
2月6日のブログでも記しましたが、明治5年(1872年)、政府は太陰太陽暦から太陽暦への改暦を布告し、その6日後に神武天皇即位を紀元とする「皇紀」を採用しました。その後、第2次世界大戦を経て「皇紀」ではなく「西暦」が中心となりました。